1. 音楽の定義
問題: 広辞苑では、音楽を「_____による芸術」と定義している。
選択肢:
A. 音
B. 言葉
C. 動き
D. 光
正解: A
説明: 広辞苑では、音楽を「音による芸術」と定義しており、音を基本的な要素として芸術的表現を行うものとされています。これは、音楽が視覚や動作ではなく、聴覚を通じて体験される芸術形式であることを強調しています。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、音楽が「音」に限定される定義が現代の多様な表現と比べてシンプルに感じられたことだ。
2. 古代ローマの哲学者
問題: 4世紀の古代ローマの哲学者アウグスティヌスは、音楽を「_____を良く整えるスキエンティアである」と定義した。
選択肢:
A. リズム
B. 音
C. 旋律
D. 和音
正解: B
説明: アウグスティヌスの『音楽論』では、「Musica est scientia bene modulandi」と述べられ、音楽は「音を良く整えるスキエンティア(知識・技術)」と定義されています。これは、音の調和や秩序を重視する当時の哲学的視点を示しています。
感想: アウグスティヌスが音楽を哲学的に捉えている点に驚き、彼の時代にもう「音」の秩序が重要視されていたとは知らなかった。
3. ジョン・ケージの定義
問題: ジョン・ケージは、「音楽は_____である。コンサートホールの中と外とを問わず、われわれを取り巻く音である」と語った。
選択肢:
A. リズム
B. 旋律
C. 音
D. 和音
正解: C
説明: ジョン・ケージは、20世紀の前衛音楽家として知られ、音楽の概念を拡張しました。彼は、音楽を単なる組織された音ではなく、日常生活の中のあらゆる音を含むものと捉えました。この考えは、彼の作品「4分33秒」などにも反映されています。
感想: ジョン・ケージの定義があまりに革新的で、日常の雑音まで音楽と考える視点に驚かされた。
4. 音楽の語源
問題: 英語の”Music”は、古代ギリシャ語の「_____」を語源とする。
選択肢:
A. mousike
B. harmonia
C. rhythmus
D. melodia
正解: A
説明: “Music”の語源は古代ギリシャ語の「mousike(ムーサの技)」であり、芸術や文化を司る女神「ムーサ(ミューズ)」に由来します。これは、音楽が芸術の一分野として神聖なものとされていたことを示しています。
感想: 音楽がミューズと結びついていると知り、神話と芸術の深い関係に驚いた。
5. 日本音楽の始まり
問題: 日本では、_____時代から既に音楽が始まっていたとされる。
選択肢:
A. 縄文
B. 弥生
C. 古墳
D. 飛鳥
正解: A
説明: 日本では、縄文時代から土笛や石笛などの原始的な楽器が発掘されており、音楽の存在が確認されています。これは、音楽が先史時代から人間の生活や儀式に深く関わっていたことを示します。
感想: 縄文時代にまで音楽の痕跡があると知り、人類の音楽への愛着の古さに驚いた。
6. 雅楽の成立
問題: 平安時代に、外来音楽を組み込んで成立した宮廷音楽は_____である。
選択肢:
A. 雅楽
B. 能楽
C. 歌謡
D. 箏曲
正解: A
説明: 雅楽は、5世紀から8世紀にかけて中国や朝鮮半島から伝わった音楽を基に、平安時代に日本独自の形で成立した宮廷音楽です。遣唐使の廃止後、国風文化が栄えた時期に発展しました。
感想: 雅楽が外来文化と日本文化の融合だと知り、その長い歴史に驚かされた。
7. 能・狂言の発展
問題: 鎌倉時代・室町時代に、猿楽から発展したものは_____である。
選択肢:
A. 雅楽
B. 能・狂言
C. 箏曲
D. 地歌
正解: B
説明: 能・狂言は、鎌倉時代から室町時代にかけて、猿楽という芸能から発展した日本の伝統芸能です。能は儀式的・劇的な要素を持ち、狂言は喜劇的な要素を持つ対照的な芸能として成立しました。
感想: 能と狂言が同じルーツから分岐したと知り、その対照的な進化に驚いた。
8. 江戸時代の音楽
問題: 江戸時代に発展した日本固有の音楽は_____と呼ばれる。
選択肢:
A. 雅楽
B. 俗楽
C. 能楽
D. 歌謡
正解: B
説明: 江戸時代には、浄瑠璃、地歌、長唄、箏曲など、日本固有の音楽が発展し、これらを総称して「俗楽」と呼びます。これは、雅楽のような宮廷音楽とは異なり、民衆の間で親しまれた音楽です。
感想: 俗楽という言葉がこんなに幅広いジャンルをカバーしていると知り、その多様性に驚いた。
9. 明治時代の音楽
問題: 明治時代以降、音楽において_____が進んだ。
選択肢:
A. 西洋化
B. 伝統化
C. 簡略化
D. 神秘化
正解: A
説明: 明治時代には、西洋文化の導入により音楽の西洋化が進み、西洋音楽の歌曲やピアノ曲が作曲されるようになりました。これは、日本の近代化の一環として行われた文化改革の一例です。
感想: 明治時代の西洋化が音楽にもこんなに大きな影響を与えたことに驚いた。
10. 昭和時代のポピュラー音楽
問題: 1920年代に始まった昭和.life時代のポピュラー音楽は_____と呼ばれる。
選択肢:
A. 歌謡曲
B. 演歌
C. J-POP
D. ロック
正解: A
説明: 1920年代には、ラジオ放送の普及とともに歌謡曲や流行歌が誕生し、昭和時代のポピュラー音楽の基礎を築きました。これは、大衆文化の普及と密接に関連しています。
感想: 歌謡曲がラジオとこんなに結びついていると知り、メディアの影響力に驚いた。
11. 1960年代の音楽
問題: 1960年代に入ると、アメリカのポピュラー音楽が取り入れられ、_____が盛んになった。
選択肢:
A. 演歌
B. ロック
C. J-POP
D. 歌謡曲
正解: B
説明: 1960年代には、ビートルズなどの影響でロックやフォークソングが日本で盛んになり、若者文化の中心となりました。これは、戦後の洋楽ブームの一環です。
感想: ビートルズが日本の音楽にこんなに大きな影響を与えたことに改めて驚いた。
12. 演歌の成立
問題: 1960年代に成立した日本独自の音楽ジャンルは_____である。
選択肢:
A. J-POP
B. ロック
C. 演歌
D. フォーク
正解: C
説明: 演歌は、1960年代に昭和の歌謡曲から派生した日本独自の音楽ジャンルで、情感を重視した歌唱スタイルが特徴です。戦後の大衆文化の中で独自の地位を築きました。
感想: 演歌が意外と最近成立したジャンルだと知り、その歴史の浅さに驚いた。
13. J-POPの成立
問題: 1990年代に成立し隆盛を迎えた音楽ジャンルは_____である。
選択肢:
A. 演歌
B. ロック
C. J-POP
D. フォーク
正解: C
説明: J-POPは、1990年代に日本のポピュラー音楽が多様化し、独自のスタイルを持つジャンルとして成立しました。アイドルやバンドなど、幅広い音楽スタイルを含みます。
感想: J-POPがこんなに最近になって定義されたと知り、その進化の速さに驚いた。
14. ラジオ放送の開始
問題: 1920年代に_____放送が開始され、音楽の大衆文化化が進んだ。
選択肢:
A. テレビ
B. ラジオ
C. インターネット
D. 新聞
正解: B
説明: 1920年代にラジオ放送が開始され、不特定多数の人々に一律の音楽を届けることが可能となり、音楽の大衆文化化が加速しました。これは、マスメディアの普及によるものです。
感想: ラジオが音楽の大衆化にこんなに大きな役割を果たしたことに驚いた。
15. 音楽産業の成立
問題: ラジオ放送の普及を基盤に、音楽の制作や流通、広告を生業とする_____会社が出現した。
選択肢:
A. レコード
B. テレビ
C. 新聞
D. 映画
正解: A
説明: ラジオ放送の普及により、音楽の需要が高まり、レコード会社が音楽の制作、流通、広告を担うようになりました。これは、音楽産業の成立を意味します。
感想: レコード会社がラジオとこんなに密接に結びついていると知り、その歴史に驚いた。
16. 新しいメディアの登場
問題: テレビなどの新しいメディアの登場と普及により、音楽愛好者はさらに_____した。
選択肢:
A. 減少
B. 増加
C. 停滞
D. 分裂
正解: B
説明: テレビの普及により、音楽番組や音楽関連のコンテンツが増え、音楽愛好者が増加しました。これは、メディアの多様化が音楽文化の拡大に寄与した例です。
感想: テレビが音楽人気をさらに広げた影響力に驚き、メディアの進化の速さを実感した。
17. 新しい媒体の出現
問題: 1980年代に_____の登場により、音楽産業は隆盛の一途をたどった。
選択肢:
A. カセットテープ
B. コンパクトディスク
C. インターネット
D. ラジオ
正解: B
説明: 1980年代にコンパクトディスク(CD)が登場し、高音質で音楽を保存・再生できるようになったことで、音楽産業は大きな成長を遂げました。
感想: CDの登場が音楽産業にこんなに劇的な影響を与えたことに驚いた。
18. 携帯音楽プレーヤー
問題: 1979年に発売された_____のような携帯音楽プレーヤーの登場で、音楽愛好者はさらに増加した。
選択肢:
A. ウォークマン
B. アイポッド
C. スマートフォン
D. ラジカセ
正解: A
説明: ソニーのウォークマンは、1979年に発売され、個人がどこでも音楽を聴けるようになり、音楽愛好者の増加に大きく貢献しました。これは、音楽のポータブル化の先駆けです。
感想: ウォークマンが音楽の持ち運びをこんなに変えたと知り、その革新性に驚いた。
19. インターネットの普及
問題: 1990年代後半に_____が普及し、音楽供給の形態が変化し始めた。
選択肢:
A. ラジオ
B. テレビ
C. インターネット
D. 新聞
正解: C
説明: 1990年代後半にインターネットが普及し、音楽のデジタル配信が可能になり、物理的な媒体を必要としない音楽供給が始まりました。これは、音楽産業に革命をもたらしました。
感想: インターネットが音楽の供給方法をこんなに短期間で変えたことに驚いた。
20. 音楽の所有形態
問題: インターネットの普及により、物として音楽を_____する需要は減少の一途をたどった。
選択肢:
A. 制作
B. 所有
C. 演奏
D. 編集
正解: B
説明: インターネットの普及により、音楽はデジタルデータとして配信されるようになり、CDなどの物理的な媒体を所有する需要が減少しました。これは、ストリーミングサービスの台頭とも関連しています。
感想: 音楽を「所有」する概念がこんなに変わったことに驚き、時代の変化を感じた。
21. 音楽のライブ
問題: インターネットの普及後も、音楽祭や演奏会は開催され続け、ライブなどはむしろ_____を迎えている。
選択肢:
A. 衰退
B. 停滞
C. 隆盛
D. 分裂
正解: C
説明: インターネットの普及により音楽のデジタル化が進んだ一方で、ライブイベントは体験型の価値が高まり、むしろ隆盛を迎えています。これは、音楽産業の新たな収益源ともなっています。
感想: デジタル化が進む中でライブが逆に盛り上がっていることに驚いた。
22. 音の要素
問題: 音には、基本周波数(音の高さ、_____)、含まれる周波数(音色、和音など)などの要素がある。
選択肢:
A. 音量
B. 音高
C. リズム
D. 方向
正解: B
説明: 音の高さは「音高」と呼ばれ、音の基本周波数によって決まります。これは、音楽の旋律や和音を構成する重要な要素です。
感想: 音の要素がこんなに科学的に分解できると知り、音楽の奥深さに驚いた。
23. 音の大きさ
問題: 音の大きさは_____と呼ばれる。
選択肢:
A. 音量
B. 音高
C. リズム
D. 音色
正解: A
説明: 音の大きさは「音量」と呼ばれ、音の強弱を表します。音楽では、音量の変化が表現の重要な手段となります。
感想: 音量が音楽の表現にこんなに影響を与えると改めて気づき、その重要性に驚いた。
24. 音の周期性
問題: 音の周期性は_____と呼ばれる。
選択肢:
A. 音量
B. 音高
C. リズム
D. 音色
正解: C
説明: 音の周期性は「リズム」と呼ばれ、音楽の拍子やテンポを構成する要素です。リズムは音楽の構造や動きを決定づける重要な要素です。
感想: リズムが音の周期性と結びついていると知り、その理論的な裏付けに驚いた。
25. 音源の方向
問題: 音の要素には、_____の方向も含まれる。
選択肢:
A. 音量
B. 音高
C. リズム
D. 音源
正解: D
説明: 音の要素には、音源の方向も含まれ、これは音がどこから聞こえるかを示します。音楽や音響技術において、立体音響などで重要な役割を果たします。
感想: 音源の方向が音楽体験に影響を与えると知り、技術の進化に驚いた。
26. J-POPの名称
問題: J-POPの名称が定着するまで時間がかかった一因として、ライバル局が「J-POP」ではなく「_____」という名称を多用したことがあげられる。
選択肢:
A. J-ROCK
B. J-SOUL
C. J-POPS
D. J-RAP
正解: C
説明: J-POPの名称が定着するまで、エフエム東京などの局では「J-POPS」という名称を多用し、「J-POP」という言葉を避ける傾向がありました。これは、メディア間の競争意識が背景にあります。
感想: J-POPとJ-POPSの名称争いがあったと知り、メディアの影響力に驚いた。
27. 音楽配信サービス
問題: 近年、_____などの音楽配信委託サービスによって、誰にでも楽曲配信が可能となった。
選択肢:
A. TuneCore
B. Spotify
C. Apple Music
D. YouTube
正解: A
説明: TuneCoreは、インディーズミュージシャンが自身の楽曲をデジタル配信できるサービスとして知られ、音楽配信の民主化に貢献しました。これは、音楽産業の構造変化の一例です。
感想: TuneCoreがインディーズにこんなに大きな影響を与えていると知り、その存在感に驚いた。
28. ストリーミングの台頭
問題: 2020年に、CD未リリースながらストリーミングで好成績を収めたYOASOBIの「_____」が年間1位を獲得した。
選択肢:
A. 夜に駆ける
B. ハルジオン
C. 群青
D. 怪物
正解: A
説明: YOASOBIの「夜に駆ける」は、2020年にストリーミングやYouTubeの再生回数で大ヒットし、Billboard Japan Hot 100の年間1位を獲得しました。これは、ストリーミング時代を象徴する出来事です。
感想: CDなしで年間1位を取ったことに驚き、ストリーミングの力を改めて感じた。
29. 洋楽離れ
問題: 日本人聴衆の楽曲を選ぶ傾向が「_____離れ」になってきていると分析されている。
選択肢:
A. 演歌
B. J-POP
C. 洋楽
D. クラシック
正解: C
説明: 日本では、K-POP市場が拡大する一方で、洋楽(英米などの音楽)の市場が縮小し、「洋楽離れ」が進んでいると分析されています。これは、文化的・社会的要因によるものです。
感想: 洋楽離れが進んでいるという分析に驚き、日本の音楽市場の変化を感じた。
30. 音楽性の要因
問題: 洋楽離れの音楽性の要因として、日本人聴衆は_____気味であることが挙げられている。
選択肢:
A. アップビート
B. ダウンビート
C. ノービート
D. オフビート
正解: B
説明: 日本人聴衆は、音楽のリズムにおいて「ダウンビート(表拍)」を好む傾向があり、洋楽の「ノリ」との違いが洋楽離れの一因とされています。これは、文化的背景の違いを反映しています。
感想: リズムの好みがこんなに文化に影響されると知り、その違いに驚いた。
31. 音楽の多様化
問題: 社会的要因として、世界的に音楽が_____していることが挙げられている。
選択肢:
A. 一極化
B. 二極化
C. 多極多様化
D. 単一化
正解: C
説明: 世界的に音楽は多極多様化しており、アメリカ一極支配が終焉し、さまざまな地域や文化の音楽が注目されるようになりました。これは、グローバル化の一側面です。
感想: 音楽が世界中で多様化していると知り、その広がりに驚いた。
32. 音楽雑誌の失墜
問題: 洋楽離れの要因として、_____などの旧来のマスメディアの失墜が挙げられている。
選択肢:
A. 音楽雑誌
B. テレビ番組
C. ラジオ番組
D. 新聞
正解: A
説明: 音楽雑誌などの旧来のマスメディアは、インターネットの普及により影響力を失い、洋楽離れの一因となりました。これは、情報発信の形態変化を反映しています。
感想: 音楽雑誌の影響力がこんなに減ったことに驚き、ネットの力を改めて実感した。
33. J-ROCKの登場
問題: 「日本の」という意味で「J-」を付ける使い方が一時期流行し、_____という表記が登場した。
選択肢:
A. J-POP
B. J-ROCK
C. J-SOUL
D. J-RAP
正解: B
説明: J-ROCKは、日本のロック音楽を指す言葉として登場し、「J-」を付ける流行の一例です。現在では、J-POPがこれらのジャンルを包括する言葉として主流です。
感想: 「J-」という表記が流行した時期があったと知り、そのネーミングの流行に驚いた。
34. ニューミュージック
問題: 1970年代・1980年代に、若者向けの自作自演の音楽は「_____」と呼ばれるようになった。
選択肢:
A. フォーク
B. ロック
C. ニューミュージック
D. アイドル
正解: C
説明: ニューミュージックは、1970年代から1980年代にかけて、フォークやロックの要素を含む自作自演の音楽を指す言葉として使われました。これは、アイドル音楽との差別化を図るものでした。
感想: ニューミュージックがこんなに明確な定義を持っていたことに驚いた。
35. ディスコの流行
問題: 1970年代には、東京都新宿区歌舞伎町などで_____が流行した。
選択肢:
A. ロック
B. ディスコ
C. フォーク
D. 演歌
正解: B
説明: 1970年代には、ディスコ音楽が世界的に流行し、日本でも新宿の歌舞伎町などでディスコが人気を博しました。これは、ダンス文化の普及を反映しています。
感想: 歌舞伎町がディスコの中心だったと知り、その意外な歴史に驚いた。
36. ハイエナジー
問題: 1980年代には、_____が踊られていた。
選択肢:
A. ハイエナジー
B. ユーロビート
C. ディスコ
D. フォーク
正解: A
説明: 1980年代には、ハイエナジーというアップテンポなダンス音楽が流行し、ディスコ文化の一部として親しまれました。これは、音楽の電子化が進んだ時期でもあります。
感想: ハイエナジーがディスコの進化系だと知り、その流れに驚いた。
37. ユーロビートの流行
問題: 1980年代後半、_____の流行が日本にも及んだ。
選択肢:
A. ハイエナジー
B. ユーロビート
C. ディスコ
D. フォーク
正解: B
説明: 1980年代後半には、ヨーロッパ発のユーロビートが日本で流行し、六本木などのディスコでダンス曲として親しまれました。これは、アイドル音楽にも影響を与えました。
感想: ユーロビートが日本でこんなに人気だったと知り、その影響力に驚いた。
38. アイドルのユーロビート
問題: ユーロビートの流行を受け、アイドルでは_____らがカバー曲を発表した。
選択肢:
A. Wink
B. 中森明菜
C. 松田聖子
D. 小泉今日子
正解: A
説明: Winkは、1980年代後半にユーロビートのカバー曲を多く発表し、ユーロビートブームを牽引しました。これは、アイドルとダンス音楽の融合の一例です。
感想: Winkがユーロビートで有名だったと知り、アイドルの多様性に驚いた。
39. BPMの増加
問題: 躍動感を上げるため、_____を超える作品も現れた。
選択肢:
A. BPM100
B. BPM110
C. BPM120
D. BPM130
正解: D
説明: 1980年代末には、音楽の躍動感や密度を上げるため、BPM130を超えるアップテンポな作品が登場しました。これは、ダンス音楽の特徴を反映しています。
感想: BPM130を超える曲が当時からあったと知り、そのテンポの速さに驚いた。
40. 早口な歌
問題: 1980年代末に、TM NETWORKの「_____」を筆頭に16ビートの「早口な歌」が現れた。
選択肢:
A. Get Wild
B. Self Control
C. Be Together
D. Beyond the Time
正解: B
説明: TM NETWORKの「Self Control」は、16ビートのリズムに乗せた早口な歌唱が特徴で、1980年代末の音楽トレンドを象徴する作品です。
感想: TM NETWORKが早口な歌で流行ったと知り、その斬新さに驚いた。
41. ジャングルの特徴
問題: ジャングルは、_____を多用して制作される音楽ジャンルのひとつである。
選択肢:
A. シンセサイザー
B. サンプラー
C. ギター
D. ドラムマシン
正解: B
説明: ジャングルは、1990年代に興った音楽ジャンルで、サンプラーを用いてブレイクビーツを高速で再生することが特徴です。これは、電子音楽の発展を示しています。
感想: ジャングルがサンプラーに依存していると知り、技術の進化に驚いた。
42. ブレイクビーツ
問題: ジャングルでは、ソウルやファンクのドラムのフレーズを_____に取り込み分解、並べ替えたものを早回しで再生する。
選択肢:
A. シンセサイザー
B. サンプラー
C. ギター
D. ドラムマシン
正解: B
説明: ジャングルのブレイクビーツは、サンプラーを用いて既存のドラムフレーズを分解・再構築し、高速で再生する技法です。これは、リズムの複雑さを生み出す手段です。
感想: ブレイクビーツの作り方がこんなに複雑だと知り、その創造性に驚いた。
43. ジャングルのベース音
問題: ジャングルの特徴として、ルーズな低い_____音が挙げられる。
選択肢:
A. ギター
B. ベース
C. ドラム
D. キーボード
正解: B
説明: ジャングルでは、リズムマシンのフロアタムの音をサンプラーでピッチを落とした低いベース音が特徴的です。これは、ジャングルの重厚なサウンドを形成します。
感想: ベース音がジャングルの個性をこんなに強く作っていると知り、その効果に驚いた。
44. ジャングルの派生
問題: ジャングルから派生したジャンルとして、_____が挙げられる。
選択肢:
A. テクノ
B. ドラムンベース
C. ヒップホップ
D. レゲエ
正解: B
説明: ジャングルから派生したドラムンベースは、ジャングルの高速リズムとベースラインをさらに発展させたジャンルです。これは、電子音楽の多様化の一例です。
感想: ジャングルからドラムンベースが生まれたと知り、ジャンルの進化に驚いた。
45. ジャングルの由来
問題: ジャングルというジャンル名の由来は、ジャマイカのキングストン市にある_____が「ジャングル」と呼ばれていたこととされる。
選択肢:
A. トレンチタウン
B. モンテゴベイ
C. オーチョリオス
D. ポートアントニオ
正解: A
説明: ジャングルというジャンル名は、ジャマイカのキングストン市にあるトレンチタウンが「ジャングル」と呼ばれていたことに由来します。これは、レゲエ文化との関連性を示しています。
感想: ジャングルの名前がジャマイカに由来していると知り、その意外な繋がりに驚いた。
46. ロックの起源
問題: ロック音楽は、1950年代にアメリカ合衆国の_____音楽であるロックンロールを起源とする。
選択肢:
A. 白人
B. 黒人
C. ラテン
D. アジア
正解: B
説明: ロック音楽は、1950年代にアメリカの黒人音楽であるロックンロール、ブルース、カントリーミュージックを起源とします。これは、ロックのルーツが多文化的な背景にあることを示しています。
感想: ロックが黒人音楽から始まったと知り、その文化的背景に驚いた。
47. ロックの特徴
問題: ロック音楽は、強い_____と電気的に増幅した大音量のサウンドを特色とする。
選択肢:
A. ビート
B. 旋律
C. 和音
D. 音色
正解: A
説明: ロック音楽は、強いビートとエレキギターやドラムによる大音量のサウンドが特徴です。これは、ロックがエネルギッシュな音楽として認識される理由です。
感想: ロックのビートがこんなに強調されると知り、その力強さに驚いた。
48. ロックの絶頂期
問題: ロック音楽は、1960年代後半の米国の_____ムーブメントと同時期に絶頂期を迎えた。
選択肢:
A. ヒッピー
B. モッズ
C. パンク
D. ニューウェイヴ
正解: A
説明: ロック音楽は、1960年代後半のヒッピームーブメントやカウンターカルチャーが高揚した時代に絶頂期を迎えました。これは、ロックが社会運動と結びついたことを示しています。
感想: ロックとヒッピーがこんなに密接だと知り、その時代背景に驚いた。
49. パンクの発展
問題: 1970年代後半のパンクは、_____へと発展した。
選択肢:
A. ニューウェイヴ
B. プログレ
C. メタル
D. フォーク
正解: A
説明: 1970年代後半のパンクは、音楽的な実験やポップ要素を取り入れたニューウェイヴへと発展しました。これは、パンクの多様化を示しています。
感想: パンクからニューウェイヴへの変化がこんなにスムーズだったことに驚いた。
50. ガレージロック
問題: 2000年代以降、パンクやニューウェイヴの流れをくむ_____ロックが注目された。
選択肢:
A. ガレージ
B. プログレ
C. メタル
D. ポスト
正解: A
説明: 2000年代以降、ガレージロックは、パンクやニューウェイヴの影響を受けたバンド(例:ザ・ホワイト・ストライプス)によって注目されました。これは、ロックの回帰の一例です。
感想: ガレージロックが2000年代に再注目されたと知り、ロックの持続力に驚いた。
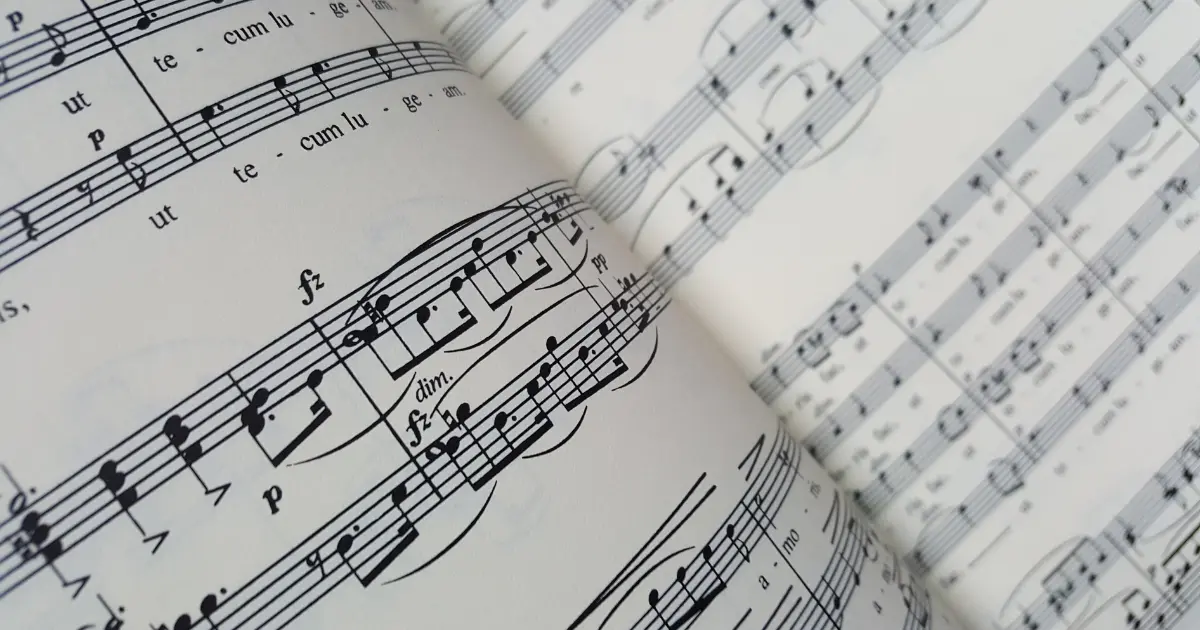


コメント